「応用情報ってどうやって対策したらいいの?」
「独学でも合格できる?」
「勉強するときに意識することは?」
応用情報技術者試験に挑むうえで、このような疑問を持っていないでしょうか?
そこで今回は、応用情報技術者試験に独学で合格した筆者がおすすめする勉強法についてご紹介します。
この記事を読むことで、応用情報の効果的な勉強方法の一例を知ることができるので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、本記事では午前試験対策についてお話ししていきます。
午後試験対策については後日公開予定です。
はじめに
筆者の情報
まず、筆者が合格した際の状況についてお話しします。
筆者は2023年にIT企業で働き始め、その年の秋季(10月)試験で応用情報に合格しています。
主な勉強法は後述する合格教本とUdemyであり、独学かつ1度目の受験で合格しました。
2023年合格と比較的最近の経験をもとにお話ししていきます。
午前試験の概要
午前試験は基本情報技術者試験の科目Aと同じような選択式であり、さらに踏み込んだ問題が出題されます。
全80問ですが、過去問がそのまま出題されていたり、少し変更されているような問題が6割程度は出題されるため、過去問での対策が非常に有効です。
応用情報に合格するには、午前と午後の両方に合格する必要があります。
午前試験を突破できなければ、午後試験の採点すらしてもらえません。
インプットとアウトプットの比率を意識する

はじめに、勉強するうえで意識すべきことについてお話ししていきます。
インプット⇒アウトプットで知識を定着させる
効率的に知識を定着させるのにおすすめな勉強法は、インプットとアウトプットを繰り返すという方法です。
具体的に、インプットは参考書などを読むことで知識を詰め込むことを言います。
また、アウトプットは問題を解く、学習した内容を書き出す、声に出すといった様に何かに対して書く・伝えることを言います。
何も意識していないと、インプットばかりの勉強になってしまう方も多いと思います。
ですが、アウトプットでの学習は知識の定着だけでなく理解不足な部分の発見にも繋がるので、意識的に取り入れていきましょう。
インプット3割、アウトプット7割の意識
具体的なインプットとアウトプットの割合はインプット3割とアウトプット7割が最も効果的とされています。
独学で応用情報合格を目指す場合、インプットでは参考書を読み、アウトプットでは過去問を解くのが良いでしょう。

筆者の場合は参考書を読むのが好きだったので、インプットが4~5割ほどでした。
特に過去問については上記でもお話しした通り、本番でそのまま出題されたり、同じような形式の問題が出題されます。
知識の定着だけでなく、本番で初見の問題が減るというメリットもある非常に有効な対策法です。
ネット上では「過去問だけ解いていればいい」といった声を見かけることもあります。
ただ、しっかりとした基礎知識を身に付けるためにも参考書でのインプットは必要な工程と言えます。
インプットのおすすめ教材

ここからは筆者が特におすすめする参考書2点をご紹介していきます。
応用情報技術者 合格教本
初めにおすすめするのは「応用情報技術者 合格教本」です。
こちらは筆者が実際に使用していた参考書です。
この参考書をおすすめするポイントは2点あります。
- 午前・午後の出題範囲をほとんど網羅できる。
- スマホで使える過去問演習ソフトが付いている。
筆者がこの本を選んだ理由は1点目の「出題範囲をほとんど網羅できる」という点でした。
また、サンプル問題も豊富に収録されているため、あまり意識せずともアウトプットを実践しながら学習を進めることができます。
欠点としては、ボリュームが多すぎるという点が挙げられます。
基礎理論などの難しい分野まで完璧にする必要はないので、ご自身が得点を稼ぎたい分野を絞って対策するのが良いでしょう。
キタミ式イラストIT塾 応用情報技術者
続いておすすめするのは「キタミ式イラストIT塾 応用情報技術者」です。
こちらは先ほどの合格教本に比べてわかりやすさ重視の参考書です。
この参考書のはフルカラーの図解が特徴で、視覚的にイメージがつかみやすい解説になっています。
文字ばかりの参考書に比べ、すらすらと読み進められるでしょう。
先ほどの合格教本に比べると学習できる範囲や深堀り具合は物足りませんが、初学者の方にはおすすめできる参考書です。
アウトプットのおすすめ勉強法

続いては、アウトプットでのおすすめ勉強法についてご紹介していきます。
知識定着にはUdemyがおすすめ
筆者がアウトプット学習に活用していたのはUdemyです。
上記の講座では過去問をベースに解説されています。
そのため、過去問を解く⇒Udemyで解説を聞くという繰り返しで学習を進めました。
Udemyは通常の通信教材に比べると安価なので、気軽に活用することができます。
参考書だけでは理解しきれない部分がある方や過去問の解説を聞きたいという方は活用を検討してみましょう。
過去問道場も効果的
応用情報の学習では過去問道場というサイトでの対策も非常に有効です。
分野ごとや年度別に過去問を解くことができ、それぞれの問題の解説を見ることもできます。
スマホでも見やすいサイトなので、通勤・通学中などの隙間時間にはぴったりの学習法です。
丁寧な解説は必要ない、少しでも安価で合格を目指したいという方は積極的に活用しましょう。
なお、合格教本などの一部の参考書には過去問を解けるアプリが付いており、そちらの方が自分好みの設定で模擬試験を行うことができます。
「過去問道場だけでいいじゃん!」ということにはならないのでご安心ください。
まとめ
応用情報の勉強法について、イメージがつかめたでしょうか?
応用情報は初学者の場合、500時間が必要と言われる難関資格です。
じっくりと時間をかけて対策していきましょう!
以下、今回のまとめです。
- インプット3割・アウトプット7割を意識する。
- インプットは参考書で知識を詰め込む。
- アウトプットはUdemy、過去問道場を活用する。
.png)

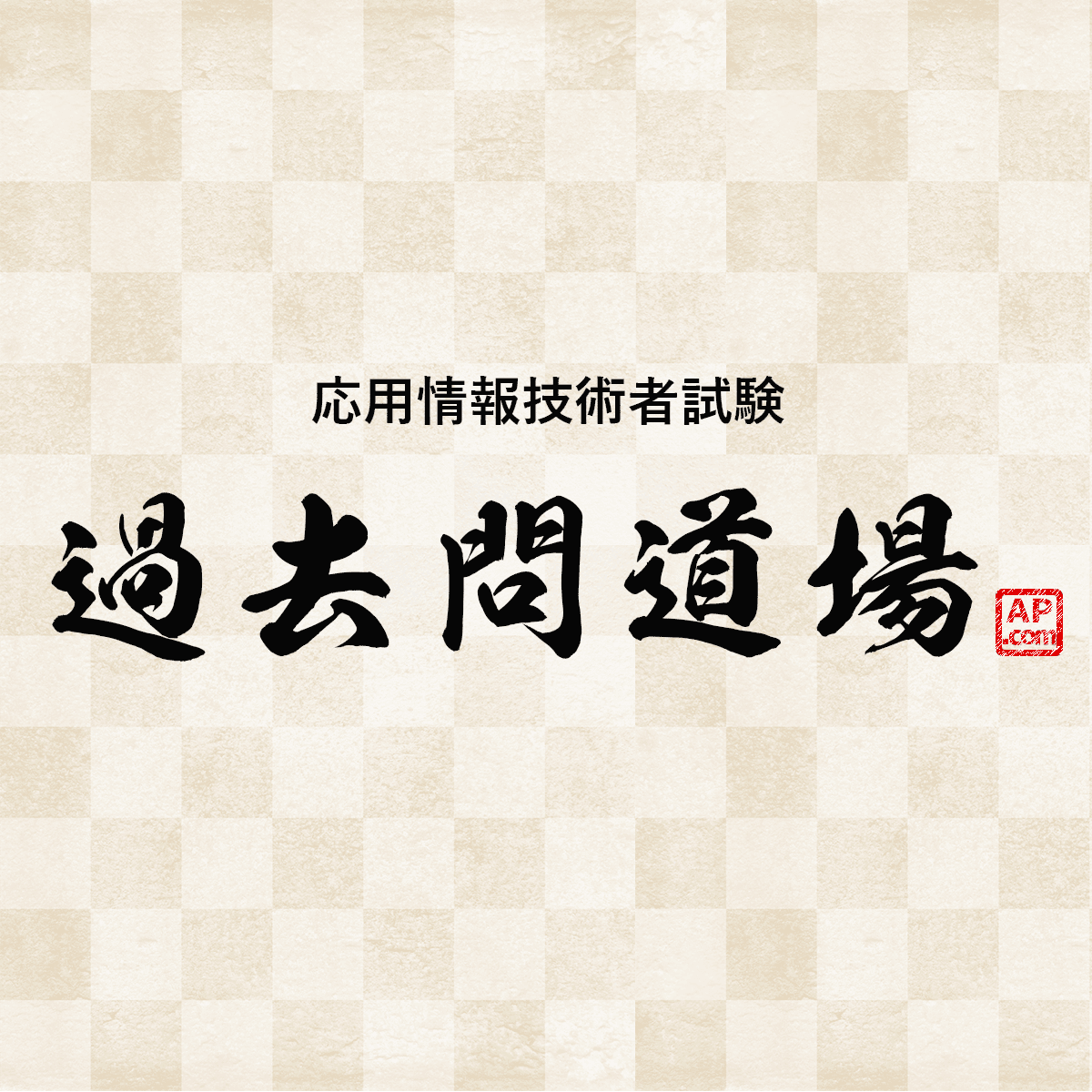


コメント